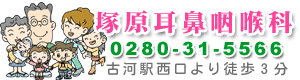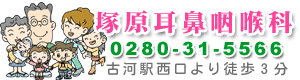|
私たちの聴力を評価する最も単純で、もっとも基本的な検査が聴力検査(オージグラム)です。耳鼻咽喉科を受診して聴覚障害が疑われる症状を訴えた場合には、先ずどの耳鼻咽喉科でもその症状を評価するにあたって、検査すると思います。皆さんの中でも耳にヘッドホンをあてて検査されたことがあるとおもいます。あるいは小学校や中学校で1度は聴力の検査を受けていると思います。
普通、音は空気中を伝わって耳に達します。これが空気伝導(気導)で、空気中を伝わってきた音は、外耳道を通って鼓膜に達し、鼓膜を振動させ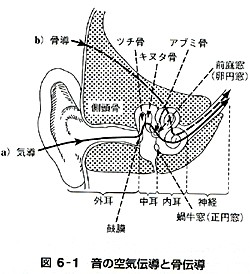 ます。鼓膜の振動はこれにつながるツチ骨、キヌタ骨を経てアブミ骨に伝わり、内耳窓のひとつである前庭窓にはめこまれているアブミ骨の底板が振動を内耳液に伝え、内耳が振動します。 ます。鼓膜の振動はこれにつながるツチ骨、キヌタ骨を経てアブミ骨に伝わり、内耳窓のひとつである前庭窓にはめこまれているアブミ骨の底板が振動を内耳液に伝え、内耳が振動します。
また、振動している物体を直接頭蓋骨にあてて音を聞くこともできます。このような音の伝わり方を骨伝導(骨導)といいます。
内耳が正常で、外耳や中耳に音の伝導を阻害する何らかの障害がある時は、気導による伝達は障害されますが、骨導による伝達は障害されません。
そこで、通常の気導音による聴力と同時に骨導音による聴力も測定すれば、障害が外耳、中耳にあるのか、内耳以後にあるのかを鑑別することができます。外耳、中耳による障害による難聴を伝音難聴、内耳以後の障害を感音難聴といいます。またその両者が混合した難聴を混合性難聴といます。
まず、聴力検査をする場所を説明します。
私どもの診療所では聴力検査の器械は2台あり、1台は診察室に設置した1人用の防音室で検査をします。この場合、閉所が苦手な方や小さいお子さんでご家族の方が同伴されないとできないような場合や、やはりご年配でご家族が同伴されていたほうがよい場合には、別の独立した検査室で、看護師が相対で検査させていただきます。患者さんの検査の理解度や、具合を見ながらやれます。下が検査中の写真です。 |